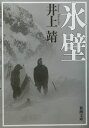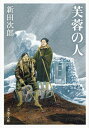-

-
【山の本棚1】井上靖『氷壁』から新田次郎『孤高の人』へ
関心のままに手元に置いてきた山の本を並べると、本棚の一区画を占めるようになってきました。 本の背表紙を見やるだけで、まだ見ぬ山旅へと誘い、過ごした山旅を回想させてくれます。 ...
続きを見る
兄弟小説
『孤高の人』に勢いを得たかのように、新田次郎は続いて現役の登山家・芳野満彦(1931-2012)モデルに、『栄光の岩壁』(新潮文庫上・下)を書きあげます。
若い日に、これも面白く読んだ。
ヨーロッパアルプスのマッターホルンの岩壁を登攀した物語です。
青春を登山とともに過ごした芳野に、新田は戦前の加藤文太郎に匹敵する戦後登山家を芳野に見た。
『孤高の人』『栄光の岩壁』とも、山岳雑誌の老舗『山と渓谷』(通称ヤマケイ)に連載された。
私の手元にあるヤマケイの一番古いものは1972年6月号で、『栄光の岩壁』の連載48回、長丁場の連載。
撤退したアイガー北壁登攀への執念の場面だ。
単行本(1973年)のあとがきで新田はこう書いています。
「孤高の人」はなぜ山に登るかという問題に対する具体的な回答として書いたものだが、「孤高の人」だけでは書き足らなかったので、「栄光の岩壁」において再びこの問題と取り組んだ。従って、私がこの小説を書こうとした姿勢は「孤高の人」と同位に立ったものであり、この二つの小説は、兄弟のようなものである。
『栄光の岩壁』モデル、登山家・芳野満彦
芳野は画文をよくし、著作『山靴の音』(ヤマケイ文庫)があります。
この原稿を書くのに、久しぶりにページをめくりますと(二見書房版)、若い日に記憶に残った質素で的確なスケッチがよみがえりました。
厳冬期の徳沢小屋(『氷壁』で既出)の小屋番を一人でしたこと、北アルプス穂高の岩壁、南アルプス北岳バットレスの岩壁など、青春を登山に注ぎ込んだ強烈な意思と個性が、弾力性ある筆で描かれます。
女性が主人公の登山小説
新田の『芙蓉の人』(文春文庫)はやはりモデルのある作品。
富士山山頂の冬季気象観測を支える明治の女性の信念と生き方を描く。
新田自らが気象庁に勤務していた経験が、反映されている。苛酷な自然につぶされそうになりながら必死に耐える山の人を壮絶に描いて、新田の真骨頂がここでも発揮されている。
同じく女性を主人公にし『銀嶺の人』(新潮文庫上・下)があるが、読む機会がないままになっている。
『聖職の碑』~学校登山:実在の中央アルプス遭難~
実在の中央アルプス遭難(大正2年8月)に題材をとり書きおろしたのが『聖職の碑』(講談社文庫)。
白樺派の文化活動の流行を背に、学校教育の中に生徒の心身や知的好奇心を促すことなどを目的にし、学校登山を試みます。
しかし、刻々と悪化する天候、避難時に頼りにした山小屋の荒廃などから、ついに登山隊はバラバラになり、死の山に転じます。
標高3千mの高山帯には身を守ってくれる障害物はありません。
子供たちは次々に倒れます。
意思もなくあてもなく、体に宿る生命の残り火をかざして彷徨するだけの少年にも暴風雨は容赦しません。
風雨に殴られ体温を奪われ死に至る少年、幸運にも森林に迷い下り、あるいは台風の一夜を先生と岩の隙間に体を寄せ合い朝日の光を浴びて生に還る描写がすさまじい迫力です。
木曽駒ケ岳山頂から北東に伸びる尾根に、作中に出てくる大きな遭難記念碑が立っている。
砂地とハイマツの高山帯です。
大人の身長をはるかにしのぐほどに大きくどっしりとしていて、圧倒されます。
『聖職の碑』では、その記念碑が堂々としていることについても一考しています。
信濃教育界の時代背景への目配りもある作品です。
取材記で当時の参加生徒を訪ねるところなどは、ノンフィクションの緊張感があります。
駒ケ根市側からだとケーブルカーで山頂近くまで入山できる木曽駒ケ岳ですが、この記念碑を目にするには、山頂から一足が必要です。
信州大学演習林の管理棟のある伊那市桂木場から入山すると、自ずとこの記念碑そばを歩くことになります。
伊那側ルートだと、森林限界を過ぎてやや平坦なところに、西駒ケ岳山荘という山小屋があります。
大正の遭難への反省から登山者が避難できる施設として建てられ、手を入れながら今日に至っているそうです。
このブログの本編『山と海と風と、空』でも、木曽福島から中央アルプス越えをしたときに、遭難碑には触れました。
未踏峰:剣岳
『剱岳・点の記』(文春文庫)は、未踏の岩峰といわれた剱岳初登を命ぜられた測量隊(明治時代)の苦闘を描く。
剱岳斜面の谷を埋める分厚い万年雪が氷河であることがわかり、最近の話題になりました。
現代では夏の最盛期には、山頂直下の鎖場で登る順番待ちが出るほどの人気の一座です。
私は三度剱岳の山頂に立ちましたが、険悪な岩場の連続は、ハシゴや鎖なしにはとても登れません。
『聖職の碑』『剱岳・点の記』とも巻末に新田の取材過程が終章に記されている。
作品に対する新田の思いの強さを感じさせ、暗い映画館でエンディングロールを静かにみつめているような気持ちになります。
剱岳は実は奈良時代に登られていたことが、測量隊が山頂で発見した錫杖によって判明。
槍ヶ岳開山ものがたり
測量隊の登頂は長い空白期を経た現代の開山といえるが、『槍ヶ岳開山』(文春文庫)は文字通りの開山物語。
仏教僧による開山の苦闘を物語る。
日本アルプスのスーパースターたち
こうした作品群を貫く現場は3千m級の山岳です。
木曽駒ケ岳、剱岳、槍ヶ岳とも3千m級山岳。
日本アルプスのスーパースターたち。
著名な山岳には、なにか特筆に値する人臭い出来事がからむものなのかも知れません。
三山とも『日本百名山』に入るべくして入っていて、百山踏破を試みる巡礼者があとを絶ちません。
-



-
【山の本棚3】新田次郎の世界②
映画でもヒット~『八甲田山死の彷徨』 映画でもヒットした『八甲田山死の彷徨』(新潮文庫)は、明治期の軍隊の雪中行軍訓練の大遭難を描きます。 八甲田山死の彷徨 (新潮文庫) ...
続きを見る
本記事に出てきた書籍まとめ
この記事の中に出てきた本を一覧にしました。
もし興味があれば、手にとってみください。
本記事に出てきた作品
- 『氷壁』
- 『栄光の岩壁』
- 『山靴の音』
- 芙蓉の人
- 銀嶺の人
- 聖職の碑
- 劔岳
- 槍ヶ岳開山
- 山と溪谷
-



-
【山の本棚3】新田次郎の世界②
映画でもヒット~『八甲田山死の彷徨』 映画でもヒットした『八甲田山死の彷徨』(新潮文庫)は、明治期の軍隊の雪中行軍訓練の大遭難を描きます。 八甲田山死の彷徨 (新潮文庫) ...
続きを見る